東日本大震災で亡くなられた多くの方々のご冥福をお祈りします。
また震災後に被災地域や移転先で苦労されている被災者の皆様をメンタルコミュニケーションリサーチ(MCR)は応援しています。
| 被災地に近い仙台・東北大学を中心に活動するMCR仙台支部では、被災者の皆様が抱える様々な不安や悩みに対し、中長期的にサポートしていきたいとの思いから電話相談窓口を開設しました。 |
<活動について紹介された記事>
◎震災を機に「悪化した人」、「社会復帰できた人」~引きこもりの命運を分けた家族の言葉と行動
東北大学大学院教育学研究科の若島孔文准教授は、「東日本大震災PTG心理・社会支援対策室」の家族臨床心理グループのメンバーとして、被災地で支援活動を行ってきた。
3月25日から、石巻市などの避難所での心理支援や、被災地の役所職員との面談などを実施。その後、避難所や仮設住宅に「簡易こころの相談室」を開設している。一方、3月27日に「東日本大震災心理支援センター現地対策室」を設置して、様々な組織や団体のこころのケアチームに参加してきた。
こうして被災地の中で間近に被災者と接してきた若島氏によると、まず、うつや統合失調症を持っていた人たちは、震災の影響を受けて、不安が高まっているという。
「電話相談でも、対面で会えるくらいの引きこもりの人のケースでも、うつや妄想などの症状があって引きこもっている人たちは、余計に症状が悪化している感じがします。涙を流したり、また起こるのではないかという予期不安を訴えたり。元々、うつなどの既往歴のある人は、悪い方向に向かったのだと思います」
実際、私の周囲でも、震災直後、被災地の映像を見て「涙が止まらない」とか、落ち込んでしまって動けなくなる人たちがいた。
「結局、災害時のストレス反応が、そういう既往歴のある人たちにはより強く、長く見られる感じがあります」(若島氏)
◎被災地の明日を支える(4) -心理士、大人の心ケア
「今は大丈夫でも、後々に何か聞いてほしいこととか出てきたら、いつでも電話してください」臨床心理士の野口修司さんは宮城県石巻市や気仙沼市の避難所などを回り、相談窓口の電話番号を記した名刺大のカードを手渡し、一人ひとりに声をかけている。・・・
「5年は続ける」活動を手掛けるのは特定非営利活動法人メンタル・コミュニケーション・リサーチ(横浜市)。4月から月・火曜の週2回、電話相談を受け付ける。[022-352-8950(月)11:00-17:00受付] 同法人設立メンバーの若島孔文・東北大准教授は「震災直後は、物資入手や家族の捜索に神経が集中しており、「今は支援は不要」という反応が多かった。だが多少落ちついた状態に戻った時、ストレス反応などが出やすい」と指摘。「多くの被災者に長期的な支援窓口を伝えることが重要」と強調する。
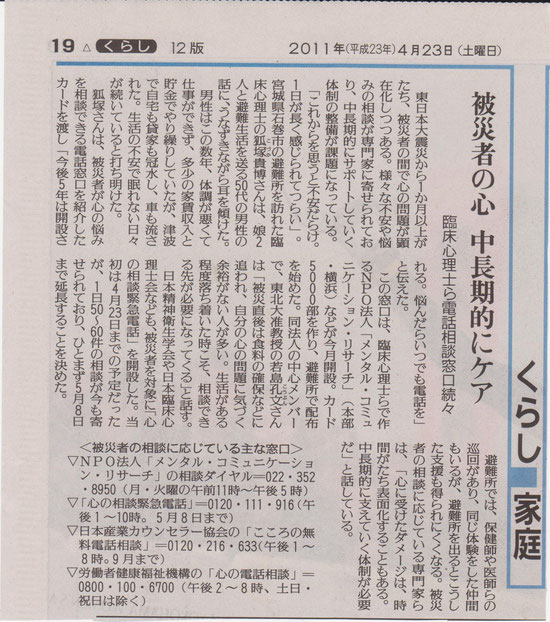
読売新聞 2011年4月23日付
◎心のケア 長期サポート -東北大グループ相談電話を開設
東日本大震災で傷ついた心のケアを長期的に行おうと、東北大大学院教育学研究科の若島孔文准教授(臨床心理学)らのグループが、5年間にわたって被災者の相談を受け付ける専用ダイヤル[022-352-8950(月)11:00-17:00受付]を開設した。電話番号を記載した名刺大のカード5000枚も作成し、避難所などで配布している。メンバーは「財布などに入れて、必要になったらいつでも連絡してほしい」と呼びかけている。
2011年4月24日




:東京都社会参加等応援事業-300x87.jpg)